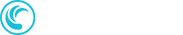仕事で使うパソコンは、家庭用とは求められる性能や選び方の基準が異なります。
ノートとデスクトップのどちらを選ぶべきか、業務に必要なスペックはどの程度か――。
本記事では、法人利用を前提としたパソコン選びのポイントを、初心者にもわかりやすく解説します。
2025年の法人向けPCのトレンド・傾向

まずは2025年の法人向けPCのトレンドや傾向を解説します。
AIに対応したNPUを搭載している
2025年の法人向けパソコン市場では、AI処理を効率的に行うためのNPU(Neural Processing Unit)を搭載した「AI PC」が注目されています。
これらのPCは、クラウドに依存せず、ローカルでAI処理を行うことができるため、セキュリティやプライバシーの観点からも優れています。
たとえば、インテルの「Core Ultra」シリーズやAMDの「Ryzen AI」シリーズなどがあり、これらのプロセッサーは高いAI処理能力があり、業務効率の向上に影響しています。
Windows 10サポート終了による移行が増加
Microsoftは、2025年10月14日にWindows 10のサポートを終了することを発表しています。
そのため、Windows 11への移行をする必要があり、パソコンの買い替え需要が高まっています。
ハイブリッドワークに適したデバイスの需要が増えている
リモートワークとオフィスワークを組み合わせたハイブリッドワークを採用する企業が増えたことで、軽量で持ち運びやすいノートパソコンやタブレットとしても使用可能な2-in-1デバイスの需要が増加しています。
パソコン選びで最初に検討すべきポイント

法人向けパソコンを選定する際、最初に検討すべきポイントは、業務内容や使用環境に適した性能と機能を見極めることです。
高性能なパソコンが必ずしもすべての業務に最適とは限らず、用途に応じた適切なスペックを選ぶことが重要です。
たとえば、営業職など外出が多い業務では、軽量でバッテリー駆動時間が長いノートパソコンが適しています。
14インチ以下のディスプレイサイズで、重量が1.5kg未満のモデルが望ましいでしょう。
一方、デスクワークが中心の事務職では、15インチ以上のディスプレイを備えたスタンダードなノートパソコンやデスクトップパソコンが適しています。
また、デザインや動画編集などのクリエイティブな業務では、高性能なCPUや大容量のメモリ、専用のグラフィックボードを搭載したパソコンが必要となります。
このように、用途に適したパソコンを選定することで、業務効率の最大化と管理負担の最小化の両立が可能となります。
情シス担当者としては、現場のニーズを正確に把握したうえで、運用面まで見据えた選定方針を検討すると良いでしょう。
持ち運ぶか?据え置きで使うか?
パソコンを選ぶ際にまず検討すべきは、『持ち運び前提か、据え置き前提か』という点です。
この判断が、ノートパソコンかデスクトップパソコンかの選択につながります。
特に法人の場合、利用者の働き方に合ったデバイス選定が、業務の効率や快適性に影響します。
外出や出張、社内での移動が多い場合には、当然ながらノートパソコンが適しています。
持ち運びを重視するなら、重量1.3kg未満・画面サイズ13.3インチ以下のモデルが理想的です。
14インチを超えると、A4サイズのバッグに収まりづらくなるため、携帯性が損なわれます。
ただし、購入時には「持ち運ぶつもり」で選んだにもかかわらず、実際には社内の自席から動かさないというケースも少なくありません。
その場合は、バッテリー性能や軽量性よりも、拡張性やコストパフォーマンスを重視したモデルが適している可能性があります。
| デスクトップ | ノートパソコン | |
| 携帯性 | ✕ | ◯ |
| コンパクトさ | ✕ | ◯ |
| 拡張(カスタマイズ)性 | ◯ | ✕ |
| 耐用年数・耐久性 | ◯ | ✕ |
| 性能に対する価格 | ◯ | ✕ |
ノートパソコンには、軽量・省スペース・オールインワン構造でセットアップが容易というメリットがあります。
ただし、性能の上限が限られ、カスタマイズが難しい点や、バッテリーの寿命、落下や衝撃による破損リスクなどがデメリットといえます。
一方のデスクトップパソコンは、高性能なCPUやグラフィックボードを搭載しやすく、同程度の性能であればノートパソコンよりも安価に導入できます。
部品単位での修理やカスタマイズが可能なため、保守性・拡張性の高さも魅力です。
ただし、据え置き前提で、持ち運びは困難なうえ、モニター・キーボード・マウスといった周辺機器が必要になる点は注意が必要です。
業務に適したパソコンスペックの選び方

パソコンを選ぶ際には、業務内容に合ったスペックかどうかを見極めることが重要です。
性能を判断するうえで注目すべき主なポイントは、「CPU」「メモリ」「ストレージ」の3点で、これらはパソコンの基本的な処理能力を左右する重要な構成要素です。
また、業務に適した「OS」や「アプリケーションソフト」の動作条件も、しっかりチェックしておきましょう。
以下では、各スペックの役割や特徴、選び方の目安について解説します。
データの制御・演算を行う「CPU」
CPU(Central Processing Unit)は、パソコンの中であらゆる処理の指示を出す“頭脳”のような存在です。
アプリケーションの起動や、ファイルの読み書き、計算処理など、すべての操作がCPUを通じて実行されます。
高性能なCPUを搭載していれば、それだけ複雑な作業でも高速にこなすことができ、業務効率の向上につながります。
CPUの性能は、「Intel Core i5」「Ryzen 7」などのグレード(シリーズ名)と、その後ろにつく世代番号によっておおよそ判断できます。
たとえば、「Core i5-1340P」は第13世代の中性能モデルであり、「Ryzen 7 7735HS」は第7世代Ryzenの上位モデルです。
数字が大きくなるほど新しい世代かつ高性能の傾向があり、複数のアプリを同時に使うマルチタスクや、動画編集など重い処理を伴う作業には、少なくとも「Core i5」または「Ryzen 5」以上を選ぶと安心です。
また、3Dモデルの操作やAI推論、CAD、データ分析などを行う部署では、CPUだけでなく、専用の画像処理チップであるGPU(グラフィックスボード)を搭載しているかも検討対象になります。
GPUは、並列演算や映像描画を高速化するため、特定用途においては業務の生産性を大きく左右します。
| スタンダード | スタンダード | ハイエンド | 超ハイエンド | |
| Intel | Core i3 | Core Ultra5、Core i5 | Core Ultra7、Core i7 | Core Ultra9、Core i9 |
| AMD | Ryzen 3 | Ryzen 5 | Ryzen 7 | Ryzen 9 |
| Qualcomm | Snapdragon X Elite、Snapdragon X Plus | |||
| 文書作成、ネット閲覧、動画視聴 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 基本的なゲーム | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 動画編集、動画配信 | ✕ | △ | ◯ | ◯ |
| 3Dコンテンツ制作、大規模言語モデル活用 | ✕ | ✕ | △ (GPU搭載推奨) | ◯ (GPU搭載推奨) |
現在の法人向けPC市場では、主にIntel、AMD、そして近年はQualcomm(Snapdragon)の3つのCPUブランドが選択肢となります。
Intel(インテル)は長年にわたりビジネスPC市場の中心を担ってきた定番ブランドで、安定性と互換性に優れているのが特長です。
とくにvPro対応モデルではセキュリティや遠隔管理など、情シス部門にとって重要な機能が強化されており、企業導入にも適しています。
AMD(エーエムディー)は、近年パフォーマンスと価格のバランスに優れた製品を多く展開しており、特にマルチコア処理に強みを持ちます。
画像編集や動画制作など、並列作業の多い用途では高いパフォーマンスを発揮します。
Qualcomm(クアルコム)のSnapdragonシリーズは、これまでスマートフォン向けとして知られてきましたが、2024年以降、Windows PC向けの「Snapdragon X Elite」などが登場し、軽量・省電力・モバイル通信の統合といったメリットを提供しています。
AI処理やバッテリー持続時間の面で特に注目されており、今後の展開が期待されているブランドです。
データを一時的に保存して処理する「メモリ」
メモリは、作業中のデータを一時的に保存する場所です。
開いているアプリケーションやブラウザ、編集中のファイルなどはすべてメモリ上に展開されて処理されます。
そのため、メモリの容量が大きいほど、複数の作業を同時に行っても動作が重くなりにくくなります。
法人向けの標準的な業務(資料作成・メール対応・Web会議など)であれば、8GBあれば問題ありません。
ただし、表計算ソフトで大規模なデータを扱う業務や、複数のソフトを同時に開いて作業するケースでは、16GB以上を選ぶと快適さが格段に向上します。
Web会議ツールやクラウドストレージなど、常時稼働するアプリが増えています。
OSの自動アップデートやセキュリティ対策ソフトも常駐するため、余裕のあるメモリ容量を確保することが、ストレスのない作業環境づくりにつながります。
| 経理事務・会計(見積書や伝票作成) | 16GB以上 |
| 営業担当者(外出や出張時の持ち歩き) | 16GB以上 |
| Webデザイン・画像編集 | 32GB以上 |
| 動画編集・ビッグデータ分析 | 32GB以上 |
データを長期的に保存する「ストレージ」
ストレージは、OSやソフトウェア、業務データなどを長期間保存するための装置です。
パソコンの保存容量に関わるストレージには、大きく分けてHDDとSSDの2種類があります。
HDDは構造がシンプルで、1TB以上の大容量でも比較的安価に導入できる点が魅力です。
ただし、読み書き速度が遅く、物理的な衝撃にも弱いため、ノートパソコンにはあまり向きません。
一方、SSDは価格がやや高めなものの、データの読み書きが非常に高速で、起動や保存動作がスムーズになります。また、モーターなどの可動部がないため、静音性や耐衝撃性にも優れています。
現在では、法人ノートパソコンの標準仕様として、256GB~512GBのSSDが主流となっています。
ストレージ選びでは、保存容量だけでなく、スピードや耐久性も含めて検討することが大切です。
| SSD | HDD | |
| データへのアクセス | 速い | 遅め |
| 衝撃への耐性 | 高い | 低い |
| 価格 | 高め | 安め |
| 容量 | 少なめ | 大容量あり |
■関連記事
SSDの規格や種類、用途に合わせた容量の選び方を解説
OSはWindows 11 Pro/Enterpriseが主流
法人向けパソコンでは、Windows 11 Enterprise またはWindows 11 Proのどちらかを選択するケースが多いでしょう。
Windows 11 Enterpriseはユーザーサブスクリプション単位のライセンスですが、Windows 11 Proはデバイス単位の永続ライセンスです。
Windows 11はセキュリティ機能が強化され、ユーザーインターフェースもより直感的に改善されています。
また、リモートワークを想定したマルチディスプレイや仮想デスクトップの使いやすさも強化されており、ハイブリッドワークにも適した設計です。
一方で、Macを業務用に導入する企業も一定数存在します。
特にクリエイティブ職では、Adobe製品との親和性やRetinaディスプレイの表示性能を評価してMacを選ぶケースがあります。
また、教育現場や小規模なチームでは、起動が速く操作がシンプルなChromebook(ChromeOS)を選ぶこともあります。
用途別にパソコンを選ぶときの注意点

パソコンを選ぶうえで大切なのは「どんな作業に使うのか」を明確にすることです。
用途がはっきりすれば、必要な性能やサイズ、形状なども自ずと決まってきます。
法人用途では、業務内容に応じた適切なスペックを選定することで、作業効率の最大化やコストの最適化が実現できます。
ネット閲覧やメール、文章作成などの軽作業をする場合
メールチェックやウェブ検索、WordやExcelを使った文書作成など、比較的軽い作業が中心となる場合は、ハイスペックなパソコンは必要ありません。
ただし、データ量の多いExcelファイルなど、複数の資料を同時に表示させながら書類を作成したりする場合、メモリは16GB以上が快適です。
| 推奨スペック | |
| OS | Windows |
| CPU | Intel Core i3/AMD Ryzen3以上 |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | SSD 256GB以上 |
伝票や見積書、プレゼン資料の作成などマルチタスクで作業したい場合
伝票や見積書、プレゼン資料を作成したり、データ分析やWebサイトの更新を行うケースなど、複数のソフトを同時に立ち上げて作業を進める機会が多い方には、ある程度しっかりした性能が求められます。
たとえば、PowerPointで資料を作りながら、ブラウザで調べものをし、TeamsやZoomで打ち合わせを行うといった一連のビジネス用途に対応できるスペックが必要です。
| 推奨スペック | |
| OS | Windows |
| CPU | Intel Core i5/AMD Ryzen 5 |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | SSD 256GB以上 |
画像や動画を編集できるハイスペックパソコンを使いたい場合
グラフィック作業や動画編集、3DCG制作といったクリエイティブ系の業務では、高い処理能力が必要です。
このような作業は大量のデータを同時に処理するため、メモリやCPU性能だけでなく、GPUの搭載も重要な要素となります。
| 推奨スペック | |
| OS | Windows/macOS |
| CPU | Intel Core i7以上/AMD Ryzen7以上/Apple M3 Pro以上 |
| メモリ | 32GB 以上 |
| ストレージ | SSD 512GB以上 |
AI処理に特化したPCを使いたい場合
2025年に入り、AI機能の活用を前提とした用途が増えてきました。
これまでのパソコンでは、CPUやGPUが主に処理を担ってきましたが、最近ではAI処理専用のNPU(Neural Processing Unit)を搭載したPCが登場し始めています。
NPUとは、AIが得意とする「推論処理」や「画像認識」「自然言語処理」などを、高速かつ低消費電力で実行するための専用チップです。
たとえば、Word文書の要約や、画像生成、音声のリアルタイム文字起こしといったタスクは、従来であればクラウドに処理を依存していました。
しかし、NPUを搭載することで、これらの処理をローカルで完結できるようになります。
そのため、インターネット接続がない環境でもAI機能が使える、情報をクラウドに送信しないためセキュリティ性が高いといったメリットが生まれます。
代表的なNPU搭載CPUには、Intelの「Core Ultra」シリーズ、AMDの「Ryzen AI」、Qualcommの「Snapdragon X Elite」などがあります。
Core Ultraは、MicrosoftのCopilotとの親和性が高く、セキュリティや管理性の面でも企業利用に向いています。
Ryzen AI(AMD)はマルチスレッド処理性能が高く、映像編集やクリエイティブ業務向けに強みがあります。
Snapdragon X(Qualcomm)は、Armベースの構造で省電力性に優れており、LTE・5G通信機能も統合されていることから、モバイルユースに特に適しています。
さらに、2024年5月にはMicrosoftが「Copilot+ PC(コパイロット プラス ピーシー)」という新しいカテゴリのPCを発表しました。
これは、40TOPS(1秒間に40兆回の演算)以上のAI演算能力を持つNPUを備えたPCで、たとえば「画面上のアクションを自動記録・検索する」「画像から背景だけを取り除く」「動画から特定のフレーズを見つけて自動で切り出す」など、より高度なAI操作を即座に実現できるのが特長です。
調達方法は購入?レンタル?それともリース?

法人でパソコンを導入する際には、「購入」「リース」「レンタル」「DaaS(Device as a Service)」といった複数の調達方法があります。
| 購入 | リース | レンタル | DaaS | |
| 契約期間 | 使用可能期間 | 2年以上 | 数日~5年程度 | 月単位、年単位契約 |
| 途中解約 | / | 不可(残リース料負担) | 可能 | 不可(残期間の費用負担) |
| 所有権 | 自社 | リース会社 | レンタル会社 | サービス提供者 |
| 修理・メンテナンス | 自社で対応 | 自社で対応 | レンタル会社が対応 | サービス提供者が対応 |
| 廃棄対応 | 自社で対応 | リース会社へ返却 | レンタル会社へ返却 | サービス提供者が対応 |
| キャッシュフロー | 一括支払い | 分割支払い | 分割支払い | 月額課金 |
| 法人税 | 資産計上 | 資産計上 | 経費計上 | 経費計上 |
一般的なのは「購入」です。自社で製品を所有するため、導入後は自由にカスタマイズでき、長期間の使用にも向いています。
たとえば、業務ソフトのインストールやセキュリティ設定を独自に施したい場合、所有権のある購入型は柔軟性が高くなります。
ただし、導入時には一括での支払いが必要になり、キャッシュフローへの影響が大きくなる点は考慮が必要です。
また、保守や修理、廃棄の手間も基本的には自社で対応することになります。
一定期間の使用を前提とした「リース」は、導入時のコストを分散しながら新品のパソコンを活用できる手段です。
契約期間は2〜5年程度が一般的で、途中解約には制限があるものの、初期費用を抑えて計画的に更新できる点は魅力です。
導入時の仕様選定にもある程度自由がきくため、「まとまった台数を導入したいが資産計上は避けたい」といった場合に適しています。
「レンタル」は、短期から中期にかけての柔軟な利用に適した調達方法です。
レンタル会社が保有する機器を借りる形式のため、契約期間が短くても対応してもらえるほか、万が一のトラブル時には保守対応もレンタル会社側が担ってくれます。
新入社員の増加や一時的なプロジェクト対応など、台数をすぐに揃えたいときに便利です。
ただし、選べる機種が在庫に限定されることや、長期間使うとリースや購入よりコストが割高になる可能性もあります。
そして注目されてきているのが、DaaS(Device as a Service)と呼ばれるサブスクリプション型の調達方法です。
これはパソコンの調達に加えて、初期設定やセキュリティ管理、故障時の対応、廃棄までを月額課金で一括して提供するサービスで、IT部門の業務負担を軽減したい企業に特に有効です。
デバイスは定期的に新しいものへと入れ替えられるため、常に最新の環境で業務を行えるのもメリットといえるでしょう。
一方で、カスタマイズの自由度が限定されるケースがあるため、導入前に提供範囲を確認することが必要です。
TD SYNNEXが提供しているDaaS
業務効率化・コスト最適化に役立つDaaSの詳細は、以下のページからご確認ください。
導入やご相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
- PCサブスクリプションサービス(PC‐DaaS) | TD SYNNEX株式会社
- PCのサブスク「DaaS(Device as a Service)」とは?メリットやリースとの違いも解説 – TD SYNNEX BLOG
まとめ:2025年の法人向けPC選びはAI用途も視野にいれる

法人向けPCの選定は、ただ高性能な製品を選べばよいというものではありません。
特に法人利用においては、業務内容や使用環境に適した機種を選ぶことが、業務効率や運用コストに大きく影響します。
2025年現在、AI処理に特化したNPU搭載PCや、Windows 11への移行による買い替え需要、ハイブリッドワークに対応した軽量デバイスなど、法人向けPCのトレンドは大きく変化しています。
ノートかデスクトップか、用途別のスペックの目安、そしてAI処理や生成系ツールへの対応といった観点から、必要な構成を見極めることが重要です。
また、調達方法についても、購入・リース・レンタル・DaaSと選択肢が広がっており、それぞれの契約形態や保守体制、キャッシュフローへの影響を比較検討することが求められます。
情シス部門としては、現場のニーズと経営的な観点の両方を踏まえ、パフォーマンスと運用効率のバランスが取れた機種・方式を選ぶことが、組織全体のパフォーマンス向上につながるでしょう。
情シス業務を支援するTD SYNNEXのPC導入・運用サポート

ここまでご紹介してきたように、法人パソコンの導入では、最新の技術トレンドやスペックの見極めに加え、業務環境や利用者のニーズを踏まえた総合的な判断が求められます。
しかし、限られた人員や時間の中で、こうした選定・導入・運用管理までをすべて自社で担うのは簡単ではありません。
そこでおすすめなのが、外部の専門パートナーによる支援の活用です。
たとえば、TD SYNNEXでは、Windows 11へのスムーズな移行をサポートするために、環境確認から最適なPC選定、キッティング、データ移行、不要機器の処分までを含む、一貫した支援サービスを提供しています。
さらに、クラウド時代に最適化された展開手法であるWindows Autopilotの活用や、PCのライフサイクル全体を見据えたITライフサイクルマネジメントサービスにも対応しており、情シス部門の負担を大幅に軽減できます。
もしパソコンの選定や移行に不安がある場合は、ぜひ以下のページよりTD SYNNEXの提供するソリューションをご確認ください。
- TD SYNNEX が提供する Windows 11 デバイス | TD SYNNEX株式会社
- クラウド時代の新しいデバイス展開 Windows Autopilot | TD SYNNEX株式会社
- ITライフサイクルマネジメントソリューションページのご紹介 | TD SYNNEX株式会社
[筆者プロフィール]
佐々木
テクニカルサポート出身のITライター。Windows Server OS、NAS、UPS、生体認証、証明書管理などの製品サポートを担当。現在は記事制作だけでなく、セキュリティ企業の集客代行を行う。