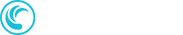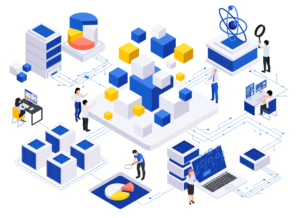現代のITインフラにおいて、サーバーの仮想化は欠かせない技術となりました。そのため、サーバーの仮想化を導入したいと考える企業や組織の担当者も多くいるでしょう。
しかし、サーバー仮想化について詳しくない方々の中には、導入に戸惑う方も少なくありません。
そこで本記事では、サーバー仮想化の基礎やハイパーバイザーの種類、仮想サーバーのメリットとデメリット、さらにはハイパーコンバージドインフラストラクチャ(HCI)という次世代の仮想化ソリューションについて、それぞれを詳しく解説します。
サーバーの仮想化とは

サーバー仮想化とは、1台の物理的なサーバー上に複数の仮想サーバーを構築する技術です。
従来は、1台のサーバーには1つのオペレーティングシステム(OS)とアプリケーションが搭載されており、そのサーバーは特定の目的に使用されていました。
しかし、サーバー仮想化により、物理サーバー上で仮想化ソフトウェアを利用して複数の仮想マシン(仮想サーバー)を作成できるようになりました。仮想マシンには独自のオペレーティングシステムとアプリケーションをインストールし、異なる用途や役割を持たせることができます。
この技術によって、1台の物理サーバーの運用管理の効率化やコストと物理的スペースの節約などのメリットがあり、サーバーの仮想化を活用する企業や組織が増えています。
ハイパーバイザーの種類
サーバー仮想化には、ハイパーバイザーと呼ばれるソフトウェアが用いられます。
ハイパーバイザーはハードウェアリソースを動的に割り当てることが可能です。これにより、仮想マシン間でのリソースの効率的な共有と制御ができます。
また、ハイパーバイザーの種類には、タイプ1(ベアメタル型ハイパーバイザー)とタイプ2(ホスト型ハイパーバイザー)が存在し、それぞれ異なる特徴があります。以下では、ハイパーバイザーの種類について解説します。
タイプ1(ベアメタル型ハイパーバイザー)
ベアメタル型ハイパーバイザーとは、物理サーバー上で直接に動作する仮想化ソフトウェアのことです。
ベアメタル型ハイパーバイザーは、物理サーバーのハードウェアリソースを仮想化し、複数のゲストOSを作成します。ホストOSを介さずにゲストOSを作成できるため、パフォーマンス性と信頼性が優れています。
代表的なベアメタル型ハイパーバイザーには、以下の製品があります。
- VMware ESX/ESXi(VMware)
- Hyper-V(Microsoft)
- Xen(XenSource) など
ベアメタル型ハイパーバイザーは、セキュリティ機能が高く評価されており、企業の基幹システムに広く採用されています。一方で、導入には一定の専門知識が必要です。
タイプ2(ホスト型ハイパーバイザー)
ホスト型ハイパーバイザーとは、既存のホストOS上に仮想化された環境を構築するソフトウェアです。
ホスト型ハイパーバイザーは、ホストOS上で仮想マシンを作成し、各仮想マシンにゲストOSをインストールします。ホストOS上で動作するため、若干の追加処理が必要になりますが、ベアメタル型ハイパーバイザーと比較すると導入しやすいです。
代表的なホスト型ハイパーバイザーには、以下の製品があります。
- VMware Server(VMware)
- Virtual PC(Microsoft)
- Parallels Desktop(Parallels)
ホスト型ハイパーバイザーは、開発・テスト環境の構築や、個人によるシステム構築など、比較的小規模な用途に向いています。
一方で、企業の基幹システムへの導入には不向きな場合が多く、基幹システムではベアメタル型が主流になっています。
その理由としては、パフォーマンス性やセキュリティ、リソース管理の柔軟性などがベアメタル型と比較すると劣っているためです。
仮想化に関する技術には、ハイパーバイザー型以外にも「コンテナ型」と呼ばれる方式も存在します。
ハイパーバイザー型とコンテナ型との違いについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。
コンテナとは?クラウドネイティブに欠かせない技術の仕組みやメリット、コンテナ運用のポイントを解説
仮想サーバーを利用するメリット

仮想サーバーを利用することで得られるメリットは、主に以下の3点があげられます。
第一に、仮想サーバーはリソースの利用効率を高めることができます。次に、システムの運用管理にかかるコストを大幅に削減することが可能です。さらに、リソースの拡張がスピーディーな点もメリットです。
以下で、それぞれのメリット について解説します。
リソースを効率的に活用できる
仮想サーバーを利用することで、物理サーバー上のリソースを複数の仮想マシン間で共有し、効率的に活用できます。これにより、アプリケーションの使用状況に応じてリソースを動的に再配分し、1つの物理サーバーで複数の異なる用途に対応することが可能です。
また、リソースの使用率が低い時間帯においても、他の仮想マシンがその余剰リソースを利用できます。結果的に、全体としてのリソースのムダを防ぎ、コスト効率の高い運用ができるようになります。
システム管理コストの削減
仮想サーバーを活用することにより、システム管理コストの削減が可能です。物理サーバーを複数設置する場合に比べ、仮想サーバーでは初期導入のハードウェア費用、設置スペース、電力消費などの削減が見込めます。
また、複数の仮想マシンを1つの物理サーバーで運用することにより、OSやアプリケーションの管理作業を一元化し、管理作業の効率化ができます。これにより、運用スタッフの作業負担軽減や、保守運用に関するコストの削減にもつながります。
リソースの拡張がスピーディー
仮想サーバーを利用する大きなメリットのひとつとして、リソースの拡張がスピーディーな点があげられます。
物理サーバーでは、サービス需要の増加に応じてCPUやメモリを物理的に追加するか、追加のサーバーを設置する必要があります。しかし、そのためには物理サーバーの拡張に伴う高いコストや長期間の準備時間が必要です。
一方で、仮想サーバーは既存の物理サーバー内で動作する仮想マシンに対して、リソースを即座に動的に再配分できます。これにより、ビジネスの成長や変動する負荷に柔軟に対応し、スピーディーにサービスの拡張や性能アップができるようになります。
仮想サーバーを利用するデメリット
仮想サーバーを使うことで多くのメリットを得られますが、その一方でいくつかのデメリットも存在します。
以下では、仮想サーバーを利用するデメリットについて解説します。
物理サーバーより性能が劣る場合がある
仮想サーバーは物理サーバーに比べて、性能面で劣る場合があります。物理サーバーではハードウェアリソースに直接アクセスが可能です。しかし、仮想サーバーの場合、仮想化ソフトウェアが間に入るため、処理効率が低下することがあります。
さらに、リソース不足の状態での仮想化や、高負荷を要するアプリケーションの運用時には、この性能差がはっきりと現れるおそれがあります。
運用管理には専門知識が必要
仮想サーバーの運用には、物理サーバーに比べてより専門的な知識を要します。仮想サーバーを利用するには、ハイパーバイザーの設定、ストレージ管理、セキュリティ対策などの専門知識が必要です。
そのため、導入時には専門的なスキルを持つスタッフの確保が重要となります。専門知識を持つスタッフがいない場合、システムの不具合やセキュリティリスクの増加が懸念されます。さらに、人材の採用や育成にかかるコストの増加といった問題もあります。
障害発生時の影響が広がる可能性がある
仮想サーバーの利用は、物理サーバーに障害が発生した際、その影響範囲が広がるリスクが伴います。1台の物理サーバー上で複数の仮想サーバーが動作するため、物理サーバーに問題が生じた場合、全ての仮想サーバーに影響を及ぼすおそれがあります。
このような状況を避けるためには、障害が発生した場合の影響範囲を事前に理解し、適切なセキュリティ対策とバックアップ計画を策定することが重要です。そのほかにも、物理サーバーの冗長化などの措置を考慮するといいでしょう。
仮想サーバーの導入事例
近年、仮想サーバーはその柔軟性とコスト効率の高さから、多くの企業や組織において重要な役割を果たしています。その具体例として、日本体育大学荏原高等学校様における仮想サーバーの導入事例を紹介します。
仮想サーバーを導入する前、日本体育大学荏原高等学校様はITシステムの老朽化や複雑さに悩まされ、それによって運用上の負荷が高まっていました。さらに、適切な管理リソースの不足、分散したシステムの保管場所、そして外部委託に伴うコストの増加などといった課題を抱えていました。
しかし、仮想サーバーの導入により、学校自身で運用できるシステムが構築でき、管理対象となるシステムを大幅に削減することに成功しました。
ハイパーコンバージドインフラストラクチャ(HCI)とは

ハイパーコンバージドインフラストラクチャ(HCI)とは、サーバーの仮想化に必要な全機能を一体化したソリューションです。このソリューションだけで、サーバーやストレージ、ネットワーク、ソフトウェアといった機能を全て備えています。
これまでのサーバーの仮想化では、物理サーバー・ストレージ専用ネットワーク(SAN)・共有ストレージの3点が必要でした。この3つのハードウェアによる仮想化構成を「3Tier型」と呼びます。この構成によって、物理サーバーの障害があってもシステムを稼働させ続けることが可能になります。
しかし、3Tier型の構成は「管理が複雑」「拡張性に欠ける」「専門スキルが必要」などの問題点を抱えていました。これらの問題を解決するために、HCIが開発されました。HCIでは、サーバー仮想化に必要な機能が備わっているため管理がしやすく、シンプルな構成で拡張しやすいなどといったメリットがあります。
TD SYNNEXでは、HPE、DELL、 Lenovo のHCIをご提案しています。
HCIに関する詳しい資料は、下記リンクよりダウンロードいただくことができます。
『仮想化環境もあって運用管理が複雑 ーHCIで複雑性解消、全社基盤をモダナイズし、DXへ向かう』
『HPE SimpliVity が“ハマる” 3つの事例』
コスト削減、運用の柔軟性などにつながる仮想サーバー。自社の状況にあわせて導入しましょう。
仮想サーバーはコスト削減、運用の柔軟性、スケーラビリティの向上などのメリットがありますが、パフォーマンスの制約やセキュリティの懸念などのデメリットも存在します。
状況に応じて適切な仮想化方法の選択と、物理サーバーとのバランスが重要です。導入には専門的な知識が必要ですが、システムの要件や目的に合わせて最適なサーバー環境を選択し、効果的な運用を行いましょう。
TD SYNNEX 株式会社では、HCI製品の導入支援を行っております。サーバーの仮想化にご興味のある方は、弊社にお気軽にご連絡ください。
[筆者プロフィール]
村田ユウジ
ITエンジニア&ライター。ソフトウェアメーカーに勤務後、ITコンサルタントへ。
集客の戦略からSEOライティング・Web広告運用まで、幅広いマーケティング活動を行う。現在、上場企業からスタートアップまで、さまざまなITジャンルの記事を執筆しています。