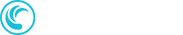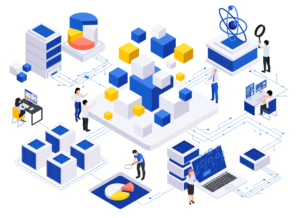クラウドが当たり前となった今、オンプレミスのみのIT基盤で本当に問題はないのでしょうか?
近年、企業のクラウド活用はさらに加速し「ハイブリッドクラウド」や「クラウドネイティブ」が大きなトレンドとなっています。
しかし、クラウドの活用が進む一方で、「既存のオンプレミス環境との統合が難しい」「セキュリティやコンプライアンスの要件を満たせるのか不安」「レガシーシステムがクラウド移行の足かせになっている」といった悩みを抱える企業も少なくありません。
本記事ではこうした課題を踏まえ、オンプレミスの活用が求められるケースとその最適な戦略について解説します。
オンプレミスとは
オンプレミス(On-Premises)とは、IT用語でサーバー機器などのハードウェアを自社運用することです。「Premises」は、英語で「家屋」「建物」「構内」「店内」といった意味で用いられる単語です。つまり「On-Premises」は「構内で(構内の)」となり、これがIT用語で「ハードウェアを自社オフィス内や企業が管理する環境で運用する」意味になりました。
もともと企業がサーバー機器を運用する際は、ハードウェアを購入し、専用の通信回線を引き、設置場所を確保してシステムを構築・運用するのが当たり前でした。
さらに、サーバーを保守・運用するには専門知識を持った人材が必要です。そのため、自社でサーバーやシステムを構築・運用するのは「大きなコストがかかる」というのが常識でした。
しかし2000年代から「クラウド」が登場し、システム運用の形態は大きく変わります。
「クラウド」は、インターネット回線を通してサーバーを利用できます。つまり、自社オフィスにハードウェアを設置したり、専門人材を確保したりする必要がなくなるということです。
結果的にシステム構築・運用の敷居が下がり、企業がビジネスにIT基盤を取り入れるのが容易になったのです。
プライベートクラウド、パブリッククラウド、オンプレミスの違いは? それぞれの特徴を徹底比較
オンプレミスのメリット・デメリット

オンプレミスのメリット
オンプレミスのメリットとしてあげられるのが「柔軟なカスタマイズが可能」です。
企業が求めるシステムは、自社独自のプロセスやルール、業界特有の要件があるため千差万別といえます。オンプレミスなら、自社要件にあったシステムを構築しやすく、業務の効率化や競争優位性を確保しやすいでしょう。
次に、「強固なセキュリティ対策」です。
オンプレミスでは、自社のセキュリティポリシーに基づいた柔軟な設計・運用が可能です。オンプレミスでは、サーバーやネットワーク機器を自社のデータセンターや社内に設置するため、厳格なセキュリティ体制を構築できます。
最後に「社内システムとの連携が容易」な点も大きなメリットです。
多くの企業では、ERP(基幹業務システム)、CRM(顧客管理システム)、会計システム、人事システムなどが長年運用されており、これらのシステムをそのまま活用したいと考えます。オンプレミスを選べば、レガシーシステムを活かしながら新しいシステムを構築しやすくなります。
オンプレミスのデメリット
オンプレミスのデメリットは「初期投資・運用費が高額」な点です。
サーバー機器の購入やネットワーク回線の構築、大規模になればデータセンターの建設など巨額の投資が必要です。さらに、システムを24時間保守・運用するための人材の確保、体制の構築も求められます。
デメリットの2点目は「導入まで時間がかかる」こと。
インフラ設計からソフトウェアの選定、システム統合、導入テストに至るまで多くのステップがあるため、システムが本稼働するまで長ければ1年以上かかるケースも珍しくありません。
オンプレミス環境とクラウド環境の違い比較
| オンプレミス | パブリッククラウド | |
| コスト | 初期費用が高額 | 初期費用が安価 |
| 維持費用 | ハードウェア・ソフトウェアの維持費用がかかる | ハードウェア等の維持費用はかからないが利用料金はかかる |
| 導入スピード | 時間がかかる | すぐに導入可能 |
| 災害対策 | 弱い(費用がかかる) | 強い |
| 障害対策 | 自社対応 | クラウド事業者対応 |
| バックアップ | 自社管理 | バックアップ可能 |
| カスタマイズ | 高度なカスタマイズが可能 | カスタマイズは限定的 |
| パフォーマンス | 高いパフォーマンスが対応可能 | 契約内容・利用環境に影響される |
| セキュリティ | 柔軟な対応が可能 | 事業者の仕様に左右される |
初期費用
オンプレミスは初期費用が高くなるということはオンプレミスのデメリットにて説明したとおりです。ハードウェアの購入やネットワーク構築、サーバールームなどの設備投資などがかかります。
クラウドはこういった初期投資が一切不要です。
維持費用
オンプレミスはハードウェアが消費する電力、ソフトウェアの更新、運用・保守といった維持コストが発生します。とくに、専門的に保守・運用できる人材を雇う必要もあります。
クラウドならハードウェアの保守はクラウド事業者が負担するため不要です(※運用は専任人材が必要なのはオンプレミスと同様)。ただし、クラウドは従量課金という形で利用した分だけの料金を支払うことになります。
導入スピード
オンプレミスはハードウェアの選定、購入、設置、設定など、多くの工程が必要です。長ければ導入までに数ヶ月~1年以上を要するケースも珍しくありません。
クラウドはオンラインで申し込めばすぐに使えるのは大きな違いといえます。スピードを求められる現代ではビジネスチャンスを逃さずにシステム構築できるのは利点でしょう。
災害対策
システムを維持しながらビジネスを継続するにはディザスタリカバリ(DR:Disaster Recovery)が必要不可欠です。地震や津波などの自然災害、テロや不正侵入などの人為的災害によってシステムが壊滅的な状況になった際に、バックアップを使って迅速に復旧しなくてはいけません。
オンプレミスはDRを自社で行うため、複数拠点にサーバーを設置してバックアップを取るなど大規模な投資が必要です。
クラウドは、クラウド事業者がデータバックアップを取ってくれるため、DRに標準対応しています。
障害対応
オンプレミスは障害が発生した際には、自社で原因の特定、復旧作業を実施する必要があります。つまり専門的な知識を持つ人材を集めて障害対応できる体制を構築しなくてはいけません。
クラウドの場合はクラウド事業者が24時間体制でシステムを監視し、障害対応してくれるため、ユーザー側の負担が軽減されます。
バックアップ
オンプレミスは自社でバックアップの計画、実施、管理が必要であり、適切なストレージやソフトウェアの選定が求められます。
一方、クラウドは自動バックアップやスナップショット機能など、クラウド事業者が提供するバックアップサービスを利用できるのでデータ保護が容易です。
バックアップの「3-2-1ルール」とは?企業におけるバックアップの重要性とその方法
カスタマイズ性の高さ
自社でサーバーやネットワーク機器を所有・管理するオンプレミスは、カスタマイズ性の高いシステム構築が可能です。
クラウドの場合は、標準化された機能だけが提供されているケースが多く、細かいニーズに対応しきれない可能性があります。サービスによってはセミカスタマイズできるものもありますが、オンプレミスほどのカスタマイズ性は期待できないでしょう。
パフォーマンス
オンプレミスはハードウェアのリソースを最大限活用できるため、高いパフォーマンスを維持できます。また、高負荷なアプリケーションやリアルタイム処理が求められる業務ではオンプレミスが有利でしょう。
クラウドはインターネットを介してリソースにアクセスするため、ネットワークの遅延や帯域幅の制限がパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
セキュリティ
オンプレミスはセキュリティポリシーや対策を自社の基準に合わせて柔軟に設定可能です。自社独自のセキュリティ要件などがある場合に効果を発揮します。
とくに社内ネットワークで閉じる構成なら外部からの攻撃にも強いのはオンプレミスを選ぶ大きな理由でしょう。
クラウドは、インターネットを通じてアクセスされるため、外部からの攻撃にさらされやすい側面があります。ただし、セキュリティパッチなどは自動で適用されるため、運用負荷は低いでしょう。
オンプレミスとクラウドのどちらを選ぶべき?

ここまでオンプレミスとクラウドの特徴を解説してきました。オンプレミス・クラウドはそれぞれ一長一短があるのがわかります。
では実際に導入を検討する際はどちらを選ぶべきなのでしょうか。
オンプレミスが向いている場合
オンプレミスが向いている場合は以下のケースです。
自社システムとの高度な連携が必要な場合
長年稼働している基幹システムと連携を考えている場合、クラウドでは制約がある可能性もあるため、オンプレミスを考慮する必要があります。
たとえば、金融・証券システムではマイクロ秒単位での処理速度が求められます。このようなケースでは、インターネット回線を利用するクラウドでは致命的な遅延を発生させるリスクがあります。一方、オンプレミスであれば、有線ネットワークによる安定した通信が期待でき有利です。
機密情報の厳格な管理が求められる場合
政府機関や医療機関などでは、システムには厳格なセキュリティ対策が求められます。データの保管場所やアクセス制御、高度な暗号化、監視体制などを実現するのであればオンプレミスのほうが細かく対応が可能です。
十分な資金と専門人材が確保できる場合
すでに触れたように、オンプレミス環境の構築・運用には、初期投資や専門知識を持つ人材が必要です。自社でこれらのリソースを確保できる場合、オンプレミス環境のメリットを最大限に活用できます。
クラウドが向いている場合
クラウドが向いているのは以下のケースです。
コストを抑えてシステムを導入したい場合
クラウドは初期費用が低く、月額料金で利用できるため、導入コストを抑えたい企業に向いています。
とくに、中小企業やスタートアップ企業ではスモールスタートが基本です。サービス初期段階では大規模な設備投資や人員確保はできないため、クラウドを使ったシステム構築が適しているでしょう。
ビジネスの変化に合わせて柔軟にシステムを拡張したい場合
クラウドでは、必要に応じてリソースを簡単に追加・削減できます。そのため、ビジネスの成長や変化に迅速に対応しながら、必要なだけシステムを拡張可能です。世界的なクラウドサービスであれば、海外リージョンも選択できるため、海外展開も容易となります。
プロジェクトメンバーが多様な働き方をする場合
クラウドは短期間での導入が可能であり、リモートアクセスも容易です。プロジェクトメンバーが一箇所に集まる必要がなく、リモートワーク主体のプロジェクトを構築しやすいでしょう。
企業におけるクラウドサービスの利用動向

引用元:総務省「令和5年通信利用動向調査の結果」
上記の表は総務省が実施した「令和5年通信利用動向調査」の結果です。
「全社的に利用している」の割合が令和3年(42.7%)→令和4年(44.9%)→令和5年(50.6%)と上昇傾向にあることがわかります。一方で「一部の事業所又は部門で利用している」は3年間横ばい傾向であり、全社的な利用に踏み切る企業が増えていることが読み取れます。
「全社的に利用している」と「一部の事業所又は部門で利用している」と合わせると令和5年は77.7%に達しており、8割近い企業がクラウドを使ったビジネスを展開しているといえます。
しかし、「利用していないし、今後も利用する予定もない」企業が10%前後いることにも注目ポイントです。依然としてオンプレミスにも根強いニーズがあることがわかります。
オンプレミスからクラウドに移行する際のポイント
昨今のトレンドとして、オンプレミスからクラウドへの移行が注目されていることがわかります。
それでは、実際にオンプレミスからクラウドへ移行する際に押さえておくべきポイントとは何でしょうか。
主なポイントとして、以下の5つが挙げられます。
- クラウドの仕様と自社要件が一致しているか
- 自社のセキュリティポリシーに対応できるか
- ランニングコストは許容できるか
- スケーラビリティは十分か
- 運用体制は構築可能か
クラウドの仕様と自社要件が一致しているか
クラウドに移行する前に、自社の業務要件とクラウドサービスの仕様が適合しているかを確認しましょう。具体的なポイントの例をあげます。
- レガシーシステムのアプリケーションがクラウド環境で動作するのか
- データベースをクラウドに移行できるか
- VPN接続や固定IPなどネットワーク要件に対応しているか
自社のセキュリティポリシーに対応できるか
セキュリティポリシーは会社によってさまざまです。クラウド移行を検討する際には、自社のセキュリティポリシーを満たせるかは重要な要素になります。具体的なポイントの例をあげます。
- エンドツーエンド(クライアントからサーバーまで)で暗号化はできるか
- ユーザーの権限を適切に管理できるか
- セキュリティログを監視できるか
ランニングコストは許容できるか
オンプレミスは初期費がかかる代わりに運用費は安くなります。一方で、クラウドは初期費用が抑えられる代わりに運用費用は契約形態によって変動するため割高になることもあります。
つまり、オンプレミスサーバーの調達費や運用費と比べてクラウドならいくらかかるのかを試算することが重要となります。
とくに「運用想定が何年なのか」「想定される利用人数やシステム負荷はどの程度なのか」によって、オンプレミスのほうが総コストは安くなるケースも。
しっかり試算することをおすすめします。
スケーラビリティは十分か
ビジネスが成長してくると、負荷の増大に合わせてシステムも拡張する必要が出てきます。そこで、想定される成長曲線にクラウドのスケーラビリティが十分かを検討する必要があります。以下が具体的なポイントの例です。
- オートスケールには対応しているか
- 海外展開を視野に入れているなら海外リージョンも利用できるか
- データベースが十分な負荷分散アーキテクチャを提供しているか
運用体制は構築可能か
クラウドは運用負荷が低いのはメリットですが、運用がなくなるわけではありません。クラウドの運用に長けた人材とシステムを適切に監視できる体制を構築する必要があります。そのため、社内のIT人材でクラウド運用体制を構築できるのかを検討するのも重要なポイントになります。
ハイブリッドクラウドの選択肢

近年では、ハイブリッドクラウドと呼ばれる構成を選択する企業も増えています。
ハイブリッドクラウドは、オンプレミスの強みを活かしつつクラウドを利用できるのが特徴です。
ハイブリッドクラウドとは
ハイブリッドクラウドとは、クラウドサービスとオンプレミスを組み合わせた構成でシステムを構築する方式です。クラウドの利点(拡張性が高い、コストを最適化できる等)と、オンプレミスの利点(セキュリティが高い、ネットワーク遅延が少ない)の両方を活かせるのが特徴です。
たとえば、自社のデータセンター(顧客管理システムや決済システム)とクラウドで動くECサイトを組み合わせる方法が考えられます。個人情報を含むような顧客データはオンプレミス環境で守りつつ、クリスマス商戦や決算セール時にはECサイトをスケールすることで、柔軟かつセキュリティ性の高いシステムが期待できます。
ハイブリッドクラウドのメリット
ハイブリッドクラウドには下記のようなメリットがあります。
コストが最適化できる
クラウドは従量課金制がメリットである一方、長期的に大量のデータを扱う場合はオンプレミスのほうがコストメリットを出しやすいです。ハイブリッドクラウドなら、頻繁に使うデータや通信はオンプレミスに任せ、処理負荷が高いもの、繁忙期などで一時的にリソースを増加させたい処理をクラウドで補う形でコストを最適化できます。
柔軟性と拡張性の向上
ハイブリッドクラウドなら通常業務をオンプレミスで運用しつつ、負荷が増大する時だけクラウドを活用できます。たとえば、前述のECサイトのセール時だけスペックをスケールする、既存のオンプレミスハードウェアではまかなえない高負荷な処理をクラウドで処理する、といったケースではハイブリッドクラウドが効果的です。
ハイブリッドクラウドのデメリット
ハイブリッドクラウドにはメリットがある一方、デメリットもあります。
運用が複雑になる
オンプレミスとクラウドの両方を管理するため、運用負荷が増加します。複数の管理ツールやダッシュボードを行ったり来たりするのは手間ですので、統合管理ツールを上手く活用できるかがポイントになります。
コスト管理が難しくなる
複数のインフラを管理する場合、オンプレミスとクラウドの両方でコストが発生します。オンプレミスは運用・保守コスト(電力、通信費や人件費)、クラウドは従量課金がかかるため、両方のコストを管理しなくてはいけません。コスト監視ツールなどを活用して急激なコスト増や予算超過を検知してアラートを受け取れるようにしましょう。
セキュリティ管理の強化が必要
ハイブリッドクラウドでは、オンプレミスとクラウド両方で異なるセキュリティ対策を適用しなければならず、リスク管理が難しいという課題があります。悪意のある攻撃者が狙ってくる侵入経路が複数あるため、ゼロトラストセキュリティの導入や適切なアクセス権管理を実施することをおすすめします。
ゼロトラストとは?従来のセキュリティモデルとの違いや、基本原則などを解説
ハイブリッドクラウドの構築におすすめのソリューション
最後にハイブリッドクラウドを実現できるソリューションを紹介します。
- HPE GreenLake
「HPE GreenLake」は、HPE社(ヒューレット・パッカード・エンタープライズ)が提供するクラウドソリューションです。パブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミスを組み合わせた柔軟なシステムを運用・管理できるのが大きな特徴。
設計段階からハイブリッドクラウドを意識した「ハイブリッドクラウド バイデザイン」により、クラウドとレガシーシステムの共存を実現できます。
「HPEが提供するすべてのソリューションを、クラウドと同等の「AS-A-SERVICE(月額・従量課金)」で利用可能!」
- DELL Technologies APEX
コンピューターテクノロジー大手のデル・テクノロジーズが提供する「DELL Technologies APEX」もハイブリッドクラウドを手軽に構築できるサービスです。企業がITインフラを持つことなく、高いセキュリティとスケーラブルなシステムを運用できます。
オンプレを“サービス”として利用する~革新的な提供モデル 「DELL Technologies APEX」
Dell APEX Data Storage Services の導入事例を下記でご紹介しています。あわせてご覧ください。
日本初 Dell APEX Data Storage Services 導入により新規サービスを展開、顧客獲得にとどまらず事業創造へ
- Lenovo TruScale
PCメーカー大手のレノボが提供する「Lenovo TruScale」は、インフラだけでなくエッジデバイスなどの導入も検討している場合におすすめのサービスです。また、特定のクラウドに依存せず、AWS、GCP、Azureなど幅広いクラウド事業者からインフラを選択できるのも特徴です。
Lenovo TruScale – Everything as-a-service
オンプレミスかクラウドか、事業にあわせて慎重に検討しましょう
クラウドの進化により、企業のIT基盤は大きく変化しています。
しかし、セキュリティやコンプライアンス、レガシーシステムとの統合など、クラウドだけでは解決しきれない課題も依然として存在するのも事実です。
もしクラウドへの全面移行を検討する場合は、自社の要件にクラウドが適合するのか、コストや運用負担は適正かを慎重に見極めることが重要です。
自社の要件に合ったオンプレミス・クラウド戦略を検討するのに本記事が参考になれば幸いです。
[筆者プロフィール]
Y.Kuroda
MLエンジニア&Web開発者&ITライター。MLエンジニアとして働きながらとSEOの知見を活かした記事を執筆しています。ライター業務を効率化するWebサービス『MOJI-KA』を開発・運用中です。