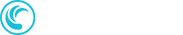SSDにはさまざまな規格や種類があり、用途に合わせてインターフェースや容量などを考慮して選ぶ必要があります。
しかし、SSD購入の際に、どれを選よば良いのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
この記事では、SSDの容量や規格の種類、用途に合った選び方、HDDとの違いなどについて、わかりやすく解説していきます。
SSDを選ぶ際の参考として、ぜひご活用ください。
SSDとは?

SSDとは、Solid State Drive(ソリッドステートドライブ)の略称です。
SSDは、内部に搭載されたフラッシュメモリと呼ばれる半導体メモリチップに、電気的な信号でデータの読み書きを行う外部記憶装置(ストレージ)の一種です。
HDDがプラッタと呼ばれる円盤型の記憶媒体を物理的に回転させ、磁気ヘッドを動かしてデータを読み書きするのに対し、SSDには物理的に動作する部品がなく、すべて電気的な信号で読み書きを行うことが特徴です。
SSDは、当初HDDと同じ接続方法や形状で1990年代に登場しました。
その後、高速な接続規格や小型な形状など、多様な種類が登場し、PC向けのストレージ市場で急速に普及が進みました。
その結果、2020年には出荷台数でHDDを上回り、SSDは外部記憶装置の主役の座を獲得しています。
SSDとHDDの違い
SSDとHDDは、いずれもデータを保存するためのストレージですが、その仕組みや特性には大きな違いがあります。
性能、動作、物理的な特徴といった観点から見た主な違いは、以下の通りです。
| 比較項目 | SSD (Solid State Drive) | HDD (Hard Disk Drive) |
|---|---|---|
| 記録方式 | SA半導体メモリ(フラッシュメモリ)に電気的に記録 | 磁性体を塗った円盤(プラッタ)に磁気的に記録 |
| 読み書き速度 | 高速 | SSDより低速 |
| 起動時間 | 短い | 長い |
| 動作音 | ほぼ無音 | あり(モーター回転音、ヘッド動作音) |
| 耐衝撃性 | 高い | 低い(衝撃で故障しやすい) |
| 消費電力 | 低い | 高い |
| サイズ・重量 | 小型・軽量 | 大型・重量あり |
| 容量単価 | 高い | 安い |
SSDのメリット

HDDと比較した場合、SSDには次のようなメリットがあります。
データの読み込みや書き込み速度が速い
SSDの最大のメリットは、データの読み書き速度がHDDに比べて速いことです。
HDDは目的のデータがある場所まで物理的に磁気ヘッドを移動させる時間や、プラッタが回転してデータがヘッド下に来るまでの待ち時間が発生しますが、SSDは半導体素子に電気的にデータの読み書きをするため、アクセス遅延がほとんどありません。
衝撃に強い
SSDには、HDDのような物理的に動作する部品が存在しません。
そのため、衝撃による故障リスクが低く、特に持ち運ぶ機会の多いノートパソコンにおいては大きな利点となります。
消費電力が少ない
HDDはデータを読み書きしていないアイドル状態でもプラッタを回転させ続ける必要があるため、常に電力を消費します。
一方、SSDはモーターなどの駆動部品を持たず、アクセスがないときはほとんど電力を消費しません。
そのため、動作中の消費電力もHDDより少なくなります。
小型化できる
物理的な駆動装置が不要なため、SSDは小型・軽量な設計が可能です。
HDDと同じ2.5インチサイズだけでなく、切手サイズに近い形状のSSDも存在し、ノートパソコンや小型PCの薄型化・軽量化に大きく貢献しています。
SSDのデメリット
多くのメリットを持つSSDですが、HDDと比較した場合に考慮すべき点もあります。
価格がHDDより高い
SSDのデメリットは、容量あたりの単価がHDDよりも高いことです。同じ予算であれば、HDDの方がより大容量のストレージを手に入れることができます。
ただし、SSDの価格は年々下落しており、特に1TB以下の容量帯では価格差は縮小傾向にあります。
フラッシュメモリが劣化する
SSDに使用されているフラッシュメモリは、書き込みのたびに半導体素子が劣化するという特性があります。
ただし、現在のSSDは「ウェアレベリング」という技術によって特定のメモリセルに書き込みが集中しないようになっているため、通常の利用では劣化による寿命を迎える心配はほとんどありません。
SSDの容量のラインナップ

SSDを選ぶ上で、性能や規格と並んで重要なのが容量です。
現在、市場には様々な容量のSSDが存在します。
一般的に流通しているSSDは、128GB、256GB、512GB、1TB、2TBなどのラインナップがあり、近年では4TB以上の大容量の製品も登場しています。
容量と価格帯を見た時に、最もコストパフォーマンスがよいのは512GB~1TBです。
なお、SSDは表示されている容量がWindowsで使用できる容量ではない点に注意しましょう。
これは、SSDメーカーが1GBを1000MBで計算していることが多いのに対し、Windowsは1GBを1024MBで計算しているためです。
さらに、使用可能な容量はOSやアプリケーションの使用する容量を差し引いて考える必要があります。
例えばWindows 11であれば、OSとOffice製品などのアプリケーション容量、SSDの動作に必要となる管理領域などによって、25~50GB程度が使用されます。
用途に合わせたSSDの容量の選び方
SSDの容量は価格に直結するため、用途に応じた容量を選ぶことが重要です。
以下に、用途別におすすめのSSDの容量の目安を紹介していきます。
メール・ネットサーフィン:128GB
PCの用途がメールの確認、ネットサーフィンといったインターネットサービスの利用が中心であれば、OSと基本的なアプリケーションが動作する128GBのSSDがあれば十分です。
作成したデータやダウンロードしたファイルなどは、必要に応じて外部ストレージまたはクラウドに保存することを考えましょう。
オフィスなどのアプリケーション:256GB
WordやExcel、PowerPointといったオフィス系アプリケーションを日常的に使用し、作成したドキュメントファイルなどをPC内に保存したいという場合は、128GBでは容量不足になる可能性があります。
そのため、256GBのSSDを選択しておくと安心です。
Web制作・DTP:512GB
Webサイト制作やDTPなどの用途で、PhotoshopやIllustratorといった専門的なアプリケーションを使用し、高解像度の画像データを多く扱う場合は、アプリケーション自体の容量も大きく、データファイルも重くなります。
そのため最低でも512GB以上の選択が推奨されます。
ゲーミング・動画編集:1TB
高画質なPCゲームは、1本あたり数十GB~100GBを超えるインストール容量が必要になることも珍しくありません。
複数のゲームをインストールしておきたい場合や、4K動画編集など大きな動画ファイルを扱う場合には、1TB以上の大容量SSDが必要になります。
SSDの規格と種類

内臓型のSSDは、PCとの接続方法である「インターフェース規格」と、物理的な形状やサイズである「フォームファクタ」によって分類されます。
ここでは、内蔵SSDの主な種類について解説していきます。
SSDのインターフェース規格と速度
インターフェース規格とは、SSDとマザーボード間でデータをやり取りするための接続ルールであり、SSDの最大転送速度を決定する重要な要素です。
SSDには主に「SATA」と「PCIe(PCI Express)」の2種類のインターフェース規格があり、それぞれに特徴があります。
以下で、それぞれの規格について詳しく説明します。
SATA
SATA(Serial ATA)は、HDDでも使われている汎用的なインターフェースです。
2025年現在、3種類の規格があります。
| 年 | 規格 | 伝送速度 | 実効レート |
|---|---|---|---|
| 2000年 | SATA1(Serial ATA 1.0) | 1.5Gbps | 150MB/s |
| 2004年 | SATA2(Serial ATA 2.0) | 3Gbps | 300MB/s |
| 2009年 | SATA3(Serial ATA 3.0) | 6Gbps | 600MB/s |
各バージョンには後方互換性があり、新しい規格のポートに古い規格のデバイスを接続しても問題なく動作します。
また、SATAには接続するデバイスや用途に応じて、コネクタの形状が異なる複数の仕様が存在します。
| コネクタ仕様 | 目的・用途 |
|---|---|
| Slimline SATA(スリムラインSATA) | ノートパソコンなどに用いるために小型化 薄型光学ドライブなどの接続に用いられる |
| Micro SATA(マイクロSATA/μSATA) | ノートパソコンなどに用いるために小型化 1.8インチのHDDやSDDなどの接続に適する |
| mSATA(Mini SATA/ミニSATA) | Micro SATAをさらに小型化 小型ノートパソコンにカード型のSSDなどを装着するのに用いられる |
SATA接続でSSDの性能を引き出すためには、AHCI(Advanced Host Controller Interface)という通信制御モードを有効にすることが一般的です。
SATA接続のSSDは、安価で互換性が高いのがメリットですが、規格上の転送速度がボトルネックとなり、それ以上に速度を上げることはできません。
PCI-e
PCI-Express(PCI-e)は、グラフィックカードなど、高速なデータ転送が必要な拡張カードを接続するために使われてきたインターフェース規格です。
SATAよりも高速なデータ転送が可能で、複数のレーンを束ねて通信帯域を広げることができます。
この高速性をSSDに応用したのがPCI-e接続のSSDです。
PCI-e接続のSSDの性能を最大限に引き出すために、NVM-e (Non-Volatile Memory Express) などの通信プロトコルが策定されています。
PCI-eには複数の世代があり、世代が上がるごとにレーンあたりの転送速度が倍増していきます。
| 年 | 規格(リビジョン) | 伝送速度/レーン |
|---|---|---|
| 2007年 | PCI-Express 2.0 (Gen2) | 5Gbps |
| 2010年 | PCI-Express 3.0 (Gen3) | 8Gbps |
| 2017年 | PCI-Express 4.0 (Gen4) | 16Gbps |
| 2019年 | PCI-Express 5.0 (Gen5) | 32Gbps |
| 2022年 | PCI-Express 6.0 (Gen6) | 64Gbps |
| 2025年(予定) | PCI-Express 7.0 (Gen7) | 128Gbps |
SSDのフォームファクタの種類
フォームファクタとは、SSD自体の物理的なサイズや形状、取り付け方法などを定めた規格のことです。
主に以下の種類があります。
2.5インチ
2.5インチはPC向けHDDと同じサイズの箱型形状をしています。
インターフェースは主にSATAが採用されており、デスクトップPCやノートPCに取り付けることができます。
HDDからの換装用途としても広く使われています。
1.8インチ
2.5インチよりもさらに小型化されたフォームファクタで、主に薄型ノートPCなどで採用されています。
接続インターフェースはMicro SATAが使われています。
mSATA
1.8インチよりもさらに小型の、基板がむき出しになったカード形状のフォームファクタです。
インターフェース名は規格名と同じmSATAです。
M.2
現在のSSDフォームファクタの主流となりつつある規格です。
小型で薄い長方形の基板形状をしており、マザーボード上にある専用のM.2スロットに直接差し込んでネジで固定します。
形状やインターフェースにより、複数の種類が存在するため、次章で詳しく解説します。
M.2 SSDについて

M.2 SSDは、新しい接続端子の規格を採用し、高速化を実現したSSDです。
ただし、従来のSATA SSDよりも規格が複雑なため、購入前に形状やインターフェースをしっかり確認する必要があります。
ここでは、M.2 SSDのサイズ、形状、インターフェース規格について説明していきます。
M.2 SSDのサイズ規格
M.2 SSDは、Type 2280のように「Type ○○○○」という形式で物理的なサイズが規定されています。
数字部分は「幅(mm)+長さ(mm)」を示しており、例えばType 2280であれば、幅22mm、長さ80mmとなります。
幅は12mm、16mm、22mm、30mmの4種類、長さは16mm、26mm、30mm、38mm、42mm、60mm、80mm、110mmの8種類が存在します。
主流はPCに利用されることが多いType 2280で、小型PCや特殊なデバイスでは、より短いType 2242などが使われます。
M.2 SSDの形状とインターフェース規格
M.2 SSDの接続端子部分には、特定のピンが欠けた切り欠きがあります。
この切り欠きの位置によって「Key ID」という種類が定められており、対応するマザーボード側のスロット形状とインターフェース規格も決まってきます。
M.2 SSDの端子形状と切り欠きの位置、主な対応インターフェースは以下の通りです。
| Key ID | 切り欠きの位置 | 主なインターフェース |
|---|---|---|
| B Key | 左側(ピン番号 12~19) | SATA、PCIe x2 |
| M Key | 右側(ピン番号 59~66) | PCIe x4、SATA |
| B&M Key | 左側 (B Key)と右側(M Key)の両方 | SATA、PCIe x2 |
SSDとHDDのどちらを選ぶか
結局のところ、SSDとHDDのどちらを選ぶべきなのでしょうか。
基本的な考え方は、速度を重視するならSSD、コストや容量を重視するならHDDです。
ここでは、「SSDを選ぶべきケース」と「HDDを選ぶべきケース」について具体的に説明していきます。
パフォーマンスを重視:SSD
ゲームや動画編集など、読み書きの速度を重視する場合にはSSDが向いています。
他にも、以下のようなケースではSSDを選ぶべきであるといえるでしょう。
- パソコンの起動を速くしたい
- アプリケーションの起動や動作をスムーズにしたい
- 重いデータを扱う作業を快適にしたい
これらの場合は、価格が多少高くてもSSDを選択するメリットが大きいといえます。
特に、操作性の向上の観点で、OSをインストールするシステムドライブにはSSDを選ぶのがおすすめです。
コストや容量を重視:HDD
大量のデータを安価に保存したい場合は、HDDが向いています。
具体的には、以下のようなケースです。
- 大量の写真、動画、音楽などのデータを保存したい
- データのバックアップ先として使いたい
- 安価に大容量のストレージを確保したい
TB単位の大容量データを保存する場合は、HDDのコストパフォーマンスはSSDよりも優れています。
なお、PCではOS/アプリ用にSSD、データ保管用にHDD、という形で2つを併用することで、両方のメリットを享受することができます。
(まとめ)用途とPCの仕様に合わせたSSDを選びましょう
SSDは、高速性、静音性、耐衝撃性といった多くのメリットから、HDDに代わるパソコンの主要な記憶装置となりました。
HDDに比べて高価であることがデメリットでしたが、SSDの普及によって価格も下がり、特に1TB以下の容量では導入しやすくなっています。
しかし、SSDには複数のインターフェース規格、フォームファクタなどがあり、多くの種類が存在します。
そのため、導入する機器の仕様をあらかじめ確認し、用途に応じた容量と性能を備えた製品を選ぶことが大切です。
PCの使用目的や構成に合わせて、最適なSSDを選定しましょう。
[筆者プロフィール]
羽守ゆき
大学を卒業後、大手IT企業に就職。システム開発、営業を経て、企業のデータ活用を支援するITコンサルタントとして10年超のキャリアを積む。官公庁、金融、メディア、メーカー、小売など携わったプロジェクトは多岐にわたる。現在もITコンサルタントに従事するかたわら、ライターとして活動中。