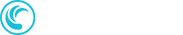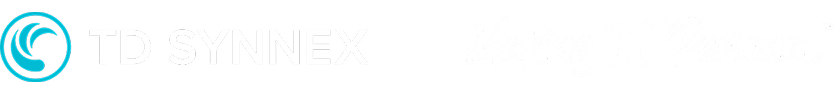生成AIとは、わかりやすく言うと「人間のように文章や画像、動画などのコンテンツを作り出すAI」です。
人間の指示に従って、膨大な学習データをもとに、新たなコンテンツを自動生成します。近年、生成AIは進化を続けており、企業の業務への利用も拡大しています。
本記事では生成AIの基本的な仕組みや種類、メリット、ビジネスシーンにおける活用事例まで詳しく解説します。
生成AIとは?
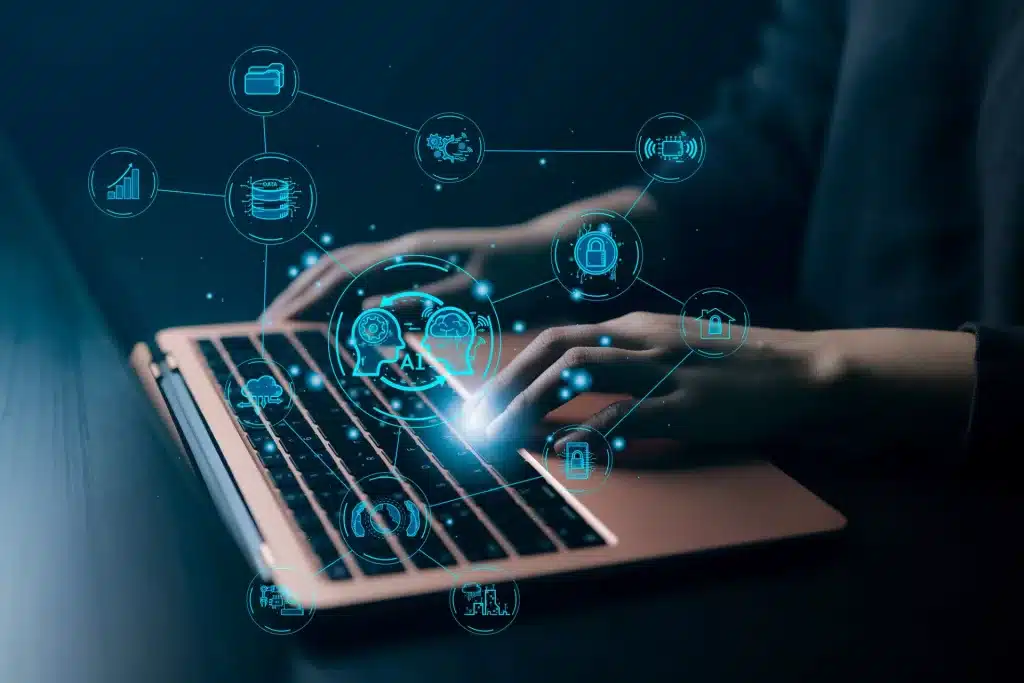
生成AIは、ユーザーの指示(プロンプト)に対して、事前に学習したデータをもとに、AIが文章や画像、プログラムコード、動画、音声などのさまざまなコンテンツを自動で生成してくれる技術です。
代表的なChatGPTは、人間の自然な言葉を理解し、会話形式でテキストを生成できる大規模言語モデル(LLM)に基づいており、継続的に改良が重ねられています。
近年は生成AIが、検索や要約・翻訳、資料作成、プログラミング補助など幅広い用途で利用されるようになりました。
総務省の「令和7年版 情報通信白書」によれば、個人利用では、特に若年層を中心に「コンテンツの要約・翻訳」、「調べもの」、「画像・動画の生成」などにおける利用が広がっており、生活に密着したツールとしての地位を確立しつつあります。
企業の業務での生成AIの利用率は55.2パーセントで、主に「メールや議事録、資料作成等の補助」などに利用されています。
このように、生成AIはテキストだけでなく、画像・音声・動画・3Dモデル・コードなど多様な形式の生成技術が実用化段階に入り、生成AI開発は今後も加速すると見込まれています。
こうした背景から、生成AIは単なるトレンドを超え、社会や産業構造を変革する基盤技術として位置づけられつつあると言えるでしょう。
生成AIが注目される理由
生成AIが注目される理由は、使いやすさと活用範囲の幅広さにあります。
人間が自然言語でプロンプトを入力すれば、生成AIによってコンテンツが自動生成されるため、ユーザーにプログラミングなどの専門的な知識がなくても気軽に利用できます。
また、文章や画像、動画、音声の生成など活用できる範囲が幅広く、さまざまな業務の効率化に役立ちます。
生成AIは近年、人間による労働に取って代わり得るものとして、大きな社会的懸念をもたらすほどに発展しつつあり、もはや無視できない存在となっています。
生成AIと従来のAIの違い
生成AIと従来のAIは、目的や主な機能、利用用途などに違いがあります。下の表に両者の比較をまとめました。
| 従来のAI | 生成AI | |
| 目的 | データの抽出・分類・予測など | コンテンツ(文章・画像・音声など)の生成 |
| 主な機能 | パターン認識、ルールベースの処理、分類など | 自然言語処理、画像生成、音声合成、コード生成など |
| 具体例 | スパムフィルター、顔認識、在庫予測、レコメンド | ChatGPT、Stable Diffusion、Sora、GitHub Copilot |
| 得意なこと | 精度の高い分類・分析 | 人間らしい表現や創造的なアウトプットの生成 |
| 主な利用用途 | 業務自動化、分析支援、異常検知など | 文章・画像の作成、プレゼン資料、会話アシスタント等 |
従来のAIは、データの抽出・分類・予測を目的に、学習データの中からプロンプトに適合する情報を「抽出」し、その結果をアウトプットすることが主な機能でした。
既存のデータをもとにした分類・分析に強みがあるため、業務では分析支援や異常検知などに活用されます。
それに対して、生成AIは、コンテンツの生成を目的としており、ユーザーの指示(プロンプト)に従って、学習データをもとにアウトプットを「新たに生成」します。
学習データの制約を受けずに独自の表現やアイデアを生成できるため、業務用の資料作成などにも活用されています。
ただし、アウトプットのクオリティは、ユーザーのプロンプトエンジニアリング(AIから望ましいアウトプットを得るために最適なプロンプトを入力するスキル)に大きく左右される点に注意が必要です。
生成AIの仕組み
こうした生成AIの根幹を支える技術が、「機械学習(machine learning)」です。
機械学習は、入力された大量のデータからパターンやルールを発見・学習し、新たに入力されたデータを分類・予測する一連の技術であり、生成AIの開発では、機械学習の中でも特に「深層学習(deep learning)」という学習方法が採用されることが一般的です。
深層学習によって、入力されたデータからより多層的に特徴量を抽出することができ、より複雑で精度の高いタスク処理が可能になります。
一般的には、こうした機械学習を経て生成された基盤モデルのうち、より具体的なタスクに適合させたものが「学習済みモデル」と呼ばれ、これを製品やサービスに組み込んだものを総称して「生成AI」と呼ばれます。
つまり、「具体的なタスク」の内容に応じて、生成AIにはさまざまな種類があるということです。
生成AIで使われている技術モデル
以下では、代表的なモデルの概要と、それぞれの主な用途・代表的なサービスを紹介します。
GPT(言語モデル)
GPT(Generative Pre-trained Transformer:生成型事前学習トランスフォーマー)は、大量の文章データを使って事前に学習を行い、その知識を活用して自然な文章を生成するモデルです。
従来のAIは、単語を順番に一つずつ処理する手法が一般的であり、長い文脈を同時に把握することが難しいという課題がありました。
一方でGPTは、文章の中で単語や文の前後関係を広く捉え、文脈全体に基づいて次に続く言葉を予測できます。
この特性により、質問への回答や要約だけでなく、コード生成など、幅広い応用が可能です。
| 主な用途 | ・自然な文章生成(会話、記事、メールなど) ・要約、翻訳、質問応答 ・コード生成 |
| 代表的なサービス | ・ChatGPT(チャット形式の対話と文書作成) ・Microsoft Copilot(WordやExcelでの文章・表の自動生成) ・GitHub Copilot(ソースコードの提案と補完) ・Bing Chat(検索結果の要約と自然言語による対話) |
VAE(変分オートエンコーダー)
VAE(Variational Autoencoder:変分オートエンコーダー)は、元のデータをいったん小さな情報に圧縮し、それをもとに似たようなデータを新たに生成する仕組みを持つ、生成AIの一種です。
通常のオートエンコーダーは、入力された画像や音声などのデータを「元通りに再現する」ことを目的とします。
それに対してVAEでは、圧縮した情報を「確率分布(ざっくりとした傾向)」として捉え、そこからランダムに値を取り出して再構成するため、まったく同一ではないものの、元データの特徴を保った多様なデータを生成することが可能です。
この特性により、VAEは「類似データの生成」や「データの補完」に強みを持ち、特に画像処理や異常検知などの分野で応用されています。
| 主な用途 | ・顔画像や手書き文字などの生成(多様なバリエーションの生成) ・画像の再構成や変換(圧縮と復元) ・入力データの特徴抽出や可視化(潜在空間による表現) ・正常データとの比較による異常検知(医療・製造業など) |
| 代表的なサービス | ・Stable Diffusion Web UI(画像生成・加工・変換) |
GAN(敵対的生成ネットワーク)
GAN(Generative Adversarial Network:敵対的生成ネットワーク)は、「生成器」と「識別器」という2つのAIモデルが互いに競い合いながら学習する構造を持つ生成モデルです。
生成器(Generator)は、本物そっくりのデータを作り出そうとし、識別器(Discriminator)は、それが本物か偽物かを見分けようとします。
両者が競争を繰り返すことで、最終的には識別器を欺けるほど高精度でリアルなデータを生成できるようになります。
このように、「本物と見分けがつかないレベルのデータ」を生成できる特性から、GANは以下に挙げる主な用途で活用されています。
| 主な用途 | ・高精度な画像生成(人物・風景・イラストなど) ・顔画像の合成やスタイル変換(年齢・表情・性別などの変更) ・低解像度画像の高解像度化(スーパーリゾリューション) ・動画のフレーム補間、アニメーション生成 ・少量データからのデータ拡張(医療・製造分野など) |
| 代表的なサービス | ・This Person Does Not Exist(実在しない人物画像の自動生成) ・Deep Art AI(写真を有名画家風に変換) ・Artbreeder(顔・風景などの合成とカスタマイズ) |
拡散モデル(Diffusion Models)
拡散モデル(Diffusion Models)は、データにノイズ(ランダムなゆらぎ)を段階的に加えた後、そのノイズを取り除いて元のデータを再現するプロセスを学習することで、新しいデータを生成するモデルです。
例えば画像の場合、元の画像に少しずつノイズを加えていき、最終的には「何が写っているか分からない砂嵐のような状態」に変化させます。
その上で、ノイズを徐々に取り除きながら画像を復元する方法を学習することで、何もない状態からでも自然な画像を描き出す能力を獲得します。
これにより、非常にリアルで高解像度な画像を生成できることが特徴です。
| 主な用途 | ・テキストからの画像生成(text-to-image) ・写真の補完や修復(画像の一部欠損を自動で補う) ・画像の変換・再構成(スタイル変更、構図調整など) ・動画や3Dモデルの生成(マルチモーダル応用) ・潜在空間を使った柔軟な編集(Latent Diffusion) |
| 代表的なサービス | ・Stable Diffusion(テキストから高品質な画像を生成) ・Midjourney(芸術性の高い画像を生成するサービス) ・DALL·E 3(OpenAIによる画像生成モデル) ・Adobe Firefly(生成AIによるデザイン・画像編集機能) |
生成AIの種類
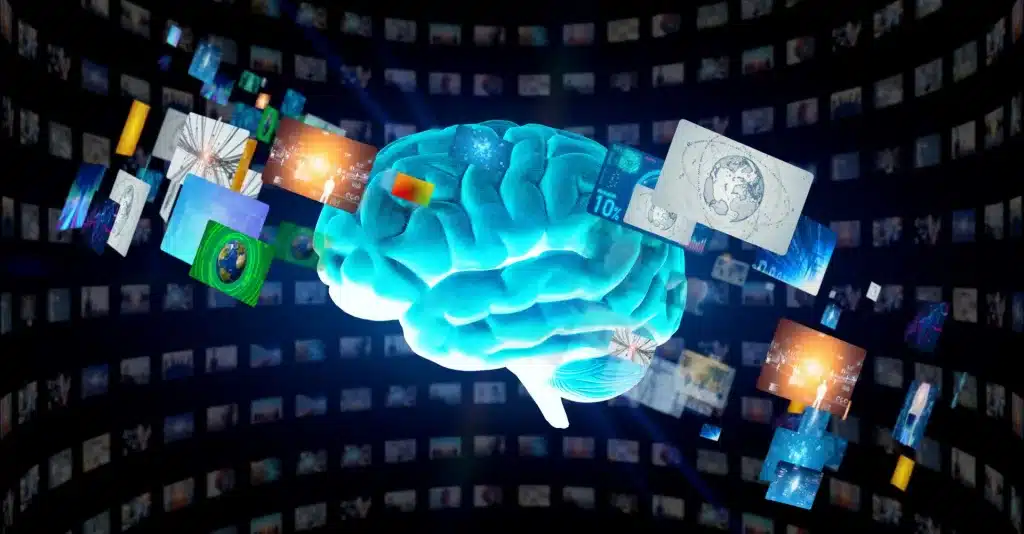
生成AIには、テキスト生成AIや画像生成AIなど複数の種類があり、生成するものによって代表的なサービスなどが異なります。
ここでは、生成AIの主な種類について解説します。
| AIの種類 | 生成するもの | 代表的なサービス | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| テキスト生成AI | テキスト(文章・会話) | ChatGPT、Claude、Gemini、Jasper | 議事録作成、メール返信、広告コピー、小説執筆など |
| 画像生成AI | 静止画(写真・イラスト) | Stable Diffusion、Midjourney、DALL·E 3 | キービジュアル制作、アイデアスケッチ、コンセプトアートなど |
| 音声生成AI | 音声データ(音声合成) | Text-to-Speech AI、Voice AI | ナレーション制作、多言語読み上げ、キャラクター音声再現など |
| 音楽生成AI | 楽曲(メロディーや歌詞) | Suno、AIVA、MuseNet | BGM制作、短尺CM曲、作曲補助、ゲーム音楽制作など |
| 動画生成AI | 映像(動画ファイル) | Sora、Runway、Pika | ショートムービー、広告映像、映像コンテンツのプロトタイピング |
| 3Dモデル生成AI | 3Dオブジェクト・構造 | LumaAI、Tripo、Meshy | ゲーム・映画のCG制作、3Dプロトタイプ、AR/VRコンテンツ開発など |
| コード生成AI | プログラムコード | Cursor、GitHub Copilot、Amazon CodeWhisperer | コーディング補助、コードレビュー、バグ修正提案、自動実装 |
テキスト生成AI
「ChatGPT」等に代表されるテキスト生成AIは「GPT-4」「GPT‑4o」等の大規模言語モデル(LLM:Large Language Model)を基盤としています。
大規模言語モデルは自然言語の取り扱いに適合させたモデルであり、数十億から数百億のパラメータを持つことで、とても自然なテキストの生成を可能にしています。
これにより、例えば、議事録の作成やメールの返信、広告コピーの作成や小説の執筆など、幅広い場面で活用することが可能です。
画像生成AI
「Stable Diffusion」や「Midjourney」に代表される画像生成AIは、テキストや画像から新たな画像を生成してくれるものです。
例えば、最終的に出力したい画像のイメージをテキストで入力するもの(t2t:text to image)や入力した画像をもとにして異なるイメージに再構成するもの(i2i:image to image)など、目的や用途に応じてさまざまなものがあります。
音声生成AI
音声生成AIは、音声データを入力すると、新たな音声データを生成してくれるAIです。例えば、ある人物やキャラクターの音声を大量に入力し学習させると、その音声でさまざまな文章を読み上げさせることができます。
さらに、特定の感情に合わせたトーンや多言語での読み上げもできることから、一度音声を学習させてしまえば、ナレーションやコールセンターの自動応答などさまざまな場面で活用することができます。
Googleの「Text-to-Speech AI」などが有名です。
音楽生成AI
音楽生成AIは、入力されたキーワードやジャンル、雰囲気などに応じて、AIが自動的に楽曲を作り出す技術です。
メロディーやコード進行、リズムパターン、歌詞など、音楽を構成するさまざまな要素をAIが組み合わせることで、オリジナルの音楽をゼロから生成します。
近年は、ボーカル付きの楽曲や、複数楽器による本格的な構成にも対応するツールが登場しており、動画やゲームのBGM生成、作曲家のアイデア出し、マーケティング用途の短尺楽曲など、幅広い場面で活用が進んでいます。
動画生成AI
動画生成AIとは、テキストや画像から、AIが映像や音源を組み合わせ、新たな動画を自動生成する技術です。
プロンプト(指示文)から直接映像を生成する「text-to-video」や、画像や既存動画を変換・補完する「image-to-video」「video-to-video」など、複数の方式があります。
最新の動画生成AIでは、人物の一貫性、空間の整合性、物理法則に沿った自然な動きなどを考慮しながら、数十秒から1分程度の動画を生成することが可能です。
音声との連携にも対応したものも登場するなど、ストーリー性のある映像や短編プロモーション動画、広告素材などの制作に活用されています。
3Dモデル生成AI
3Dモデル生成AIとは、テキストや画像から、AIが3Dモデルを自動生成する技術です。
ゲームのキャラクターやオブジェクト、アニメや映画のCGコンテンツの制作などの業界において活用することが期待されており、今勢いのある生成AIの種類の一つです。
「LumaAI」や「Tripo」、「Meshy」などが代表例です。
コード生成AI
コード生成AIは、大規模言語モデル(LLM)を基盤として、プログラミングに関する指示や文脈を読み取り、プログラムコードを自動で生成・補完することができる技術です。
自然言語で「○○を実装して」といった指示を入力するだけで、適切なコードを提案してくれるほか、既存のコードに対して改善点やエラーの指摘を行う機能を備えているものもあります。
これにより、開発作業の効率化に加え、属人化の防止や品質の安定化といった効果も期待されています。
その他の生成AI
生成AIはテキストや画像、音声、動画などの分野にとどまらず、より専門的・実務的な用途に特化した形でも発展を続けています。
例えば、プレゼン資料の自動作成に対応した生成AIは、スライド構成や図表、説明文を自動生成してくれるため、ビジネスシーンにおけるドキュメント準備の手間を大幅に軽減できます。
また、ゲーム開発に特化したシナリオ生成やキャラクター設定の補助AI、法務や医療分野の専門文書生成AIなど、業界ごとのニーズに応じた多様な生成AIが日々開発されています。
生成AI活用のメリット
企業が生成AIを活用することで、業務の効率化とコストの削減が期待できるだけでなく、発想支援や学習促進まで、幅広い領域でメリットを得られます。
例えば、資料作成や調査・情報収集といったルーチン業務に、生成AIを用いて自動化すれば、業務効率の大幅な改善が期待できます。
アイデア出し・考察などの業務では、生成AIの回答が、人では考えられないような独創的な発想となることもあるでしょう。
また、生成AIは学習やスキルアップにも貢献します。
疑問点が出てきたタイミングで生成AIに質問すれば、即座にわかりやすい回答が得られるため、効率の良い学習が可能です。
生成AIは種類が多く、現在も開発が進んでいます。
そのため、生成AIは今後も幅広い業界・業種の業務で効果を発揮していくでしょう。
生成AI活用のメリット
業務効率改善
- 資料作成の効率改善
- 調査、情報収集の高速化
- ルーチン業務の自動化
- データの整理や分析の効率改善
アイデア出し・考察
- アイデア出しや発想の支援
- 意思決定のサポート
学習・スキルアップ
- 学習・自己研鑽の効率化
- 最新動向のキャッチアップと理解促進
生成AIのビジネス活用シーン

具体的には、以下のようなビジネスシーンで生成AIを活用することが考えられます。
カスタマーサポートにおける対応の自動化やアシスト
メールの返信や電話対応などのカスタマーサポートは、日常的な業務の中でも多くの時間と労力を要する作業の一つですが、これらの業務は生成AIとの相性が良いと考えられています。
テキスト生成AI によって、顧客からの問い合わせの内容を理解して適切な文章を作成することはもちろんのこと、音声生成AIと組み合わせることで、24時間365日、自動で電話対応が可能なサービスが登場するなど、現時点でも実際に多くの企業が生成AIを導入している業務の一つです。
広告コピーやWeb記事のアイデア出しやたたき台の作成
また、前述のとおり、新たにアウトプットを生成してくれる生成AIの特徴を生かして、広告コピーやWeb記事、その他のコンテンツ制作においてアイデア出しやたたき台の作成に利用することも非常に有効な活用方法です。
商品の特徴やターゲット層、文字数などを指定してプロンプトを入力すれば、より適したアウトプットを生成することが可能であり、また、人間が考えるよりも早く多くのアイデアを出してくれることから、生産性の向上に大きく寄与してくれることでしょう。
データ分析のサポートと、レポートの自動生成
大量のデータを迅速に処理可能な生成AIは、人間が見逃してしまうパターンやトレンドを発見することも期待できることから、データの分析や予測のほか、それらをもとにしたレポートの作成にも活用することが可能です。
出力形式等を指定すれば、ニーズに応じてフォーマットをカスタマイズすることができます。
営業資料の下書きやプレゼン台本の作成
生成AIは、製品やサービスの情報、ターゲット市場、提案先の業種などをもとに、営業資料やプレゼンテーション用の台本の下書きを自動で作成できます。
特に、PowerPoint形式のスライド構成やナレーション原稿のたたき台を素早く用意できるため、企画提案や社内外向けのプレゼン業務における準備時間の短縮や、表現のブラッシュアップに活用されるケースも多いです。
業務効率化のアイデア出し
社内業務の自動化や業務フローの改善を目的としたアイデア出しにも、生成AIは有効です。
例えば、業務プロセスの簡略化、業務分担の見直し、使用ツールの改善提案など、現状の課題を入力すれば、改善に向けた多角的な選択肢を提示してくれます。
特に、これまで個人の経験や勘に頼っていた業務改善の分野において、新たな視点の発見につながります。
内容が難解、量が膨大といった読むのに時間がかかる資料の要約
法律文書や研究論文、社内マニュアルなど、専門性が高く分量が多い文書を生成AIで要約すれば、短時間で要点を把握できます。
入力する文書のフォーマットに応じて、見出し付きの要約や箇条書きのまとめ、結論と根拠の整理などが自動生成されるため、情報収集や意思決定の高速化につながります。
コード生成
生成AIは、プログラミングに関する自然言語での指示をもとに、コードの自動生成やリファクタリング、バグの検出といったタスクをサポートします。
主な活用シーンは、特定の処理を実装したい場合や、既存コードの改善点を知りたい場合などです。
非エンジニアでも簡単なスクリプトの作成や自動化の仕組みを構築できるようになるため、開発業務の効率化だけでなく、技術継承や属人化の解消といった効果も期待できます。
生成AIの利用における注意事項

生成AIは非常に強力なツールであり、多くの業務をサポートしてくれます。
一方で、その特性を正しく理解し、安全かつ効果的に活用するためには、いくつかの注意点も押さえておく必要があります。
AIの幻覚:内容の正確性は人間による検証が必要
生成AIを利用する際は内容の正確性に注意しなければなりません。
その理由は、生成AIは、学習データをもとに、プロンプトに対して確率的・統計的に見て「もっとも確からしい」回答をしているにすぎないため、虚偽の情報が出力されてしまうこともあるからです。
このような問題を一般的に「幻覚(ハルシネーション)」と呼びます。
また、生成AIによっては、学習データの取得期間に制限があるために、最新の情報が反映されていない回答を出力することもあります。
したがって、生成AIのアウトプットを業務で利用する場合には、必ず人間による品質確認や検証といった工程が必須です。
セキュリティ面:個人情報や機密情報は入力しない
企業が生成AIを利用する際に特に注意しなければならないのがセキュリティ面です。
生成AIによっては、入力したデータが機械学習に利用されてしまうものもあり、仮に個人情報や企業秘密を入力してしまうと取り返しのつかない事態になりかねません。
そのため、入力したデータの取り扱いに関しては、利用規約や社内ガイドラインなどを確認の上、必ず遵守しましょう。
法的規制:法的規制やAI倫理についてのリスクを理解・更新する
近年、生成AIに関する法的規制の在り方については、著作権法や個人情報法保護法などを中心に盛んに議論されていることに加え、業界や業種に応じて、独自のAI倫理を定めている分野もあります。
さらに2024年には、経済産業省と総務省から、AIの開発・提供・利用にあたっての必要な取り組みについて、日本におけるAIガバナンスの統一的な指針を示した「AI事業者ガイドライン」も策定・公表されています。
企業のコンプライアンスとしては、こうした法的規制やAI倫理の動向にも注意し、日々情報をアップデートしていくことも重要です。
注意点を踏まえた活用におすすめのAIソリューション

前述の注意点を踏まえて企業でAIを活用するなら、AIの機能だけでなく、セキュリティ面の安全性が高く、サポート体制が充実したソリューションを選ぶことが重要です。
それにより、企業のAI活用のリスクを抑えつつ、機能を最大限に活用した業務効率化を目指せます。
TD SYNNEXでは、企業の業務効率化に役立つ生成AIソリューションを数多くご用意しております。
業務の課題に応じたソリューションのご提案から、導入・活用のご支援まで、万全なサポート体制を整えておりますので、AIを初めて導入する企業様も安心してご利用いただけます。
TD SYNNEXでは以下のAIソリューションをご用意しております。
Azure OpenAI Service
Microsoft Azureが提供する「Azure OpenAI Service」は、OpenAI社が提供している各種AIモデルをMicrosoft Azure上で利用できる唯一のサービスです。
入力したデータが機械学習に利用されることがなく、Microsoft Azureの認証機能も使用できるため、セキュリティ面での安全性が高いのが特徴です。
さらに、Azure OpenAI Serviceは、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を専属管轄とする契約が可能であることから、法的リスクの予測可能性が高い点でもおすすめです。
Microsoft 365 Copilot
「Microsoft 365 Copilot」は、WordやExcel、PowerPointといったMicrosoftのアプリケーションとあわせて活用できるAIアシスタントです。
プレゼン資料の作成や議事録の作成、データ分析・集計など、日常業務の効率化に貢献します。
営業部門やマーケティング部門の担当者から、経営者層まで幅広くご活用いただけます。
Gemini
「Gemini」は、Googleが提供するAIアシスタントで、最先端の生成AI機能を使用して画像や文章、音声、音楽を理解・生成できます。
Google WorkspaceやGoogle Cloudと連携し、幅広い業務に活用が可能です。
例えば、業務上の資料作成やデータ分析、アイデア出しなど、さまざまな業務で効果を期待できます。
また、Gemini にはGoogleのセキュリティ基盤と保護ポリシーが適用されているため、自社の重要な情報を守りながらご利用いただけます。
HPE Private Cloud AI
「HPE Private Cloud AI」は、AI開発に必要なハードウェア・AIソフトウェア・生成AIアプリケーションといったコンポーネントを標準搭載したプライベートソリューションです。
通常のAI構築では、セキュリティやプライバシーの保護、開発環境の整備など、実際の開発までに多くの課題が存在します。
しかし、HPE Private Cloud AIは最先端技術を事前検証した上で、組み合わせて提供されているため、導入することで、迅速にAI開発に集中できる環境が整います。
顧客情報を活用したAI-OCRサービスをはじめ、コード生成・単体テストや、LLM・VLMのLoRA、フルパラメータファインチューニングの実装まで幅広くご活用いただけます。
IBM watsonx
IBMのAI開発ソリューション「watsonx.ai」が組み込まれた、オンプレミスのハードウェアもご提供しております。
データはクラウドではなくオンプレミスで扱うため、外部からの不正アクセスを軽減しつつ、自社独自のセキュリティ対策や、社内システムとの柔軟な連携を実現します。
レノボ、DELL、HPEの中から、ご希望のサーバーをお選びいただくことが可能です。
適切なリスク対策を行い、生成AIサービスを活用する

日々続々と登場する生成AIサービスは、有効に活用すれば、業務の大幅な効率化やコストの削減が期待できます。
一方で、生成AIサービスを有効に活用するためには、そのリスクを正しく把握した上で、導入を考えている業務との関係で、どのような機能や仕様であればそのリスクを抑えることができるのかを慎重に検討することが重要です。
特に企業においては、社内ガイドラインの策定や従業員への周知、トレーニングの実施といった対策も重要であり、生成AIサービスを業務に導入するにあたっては、このような多角的視点で、各サービスを比較検討すると良いでしょう。
TD SYNNEXではAI導入のご相談も承っておりますので、ご検討中の担当者様はお気軽にお問い合わせください。
【筆者プロフィール】
河瀬季/かわせ・とき
モノリス法律事務所 代表弁護士
小3でプログラミングを始め、19歳よりIT事業を開始。
ベンチャー経営を経て、東京大学法科大学院に入学し、弁護士に。
モノリス法律事務所を設立し、ITへの知見を活かして、IT・ベンチャー企業を中心に累計1,075社をクライアントとしている。